かつて世界の半導体市場を席巻した日本。NEC、東芝、三菱電機――総合電機型経営が生んだ垂直統合モデルは、技術と市場を同時に制し、世界シェアの過半数を占める黄金期を築いた。しかし1990年代後半以降、政策の転換、企業文化の硬直、そしてグローバル競争の波に飲まれ、30年にわたる凋落の道をたどる。なぜ日本の半導体産業は凋落したのか、世界の情報通信分野の最新トレンドを長年取材してきた日本屈指のITジャーナリストであり、日本パブリックリレーションズ学会の特別研究会「失われた30年検証研究会」チーフリサーチャー、IT調査コンサルティング会社、MM総研の代表取締役所長である関口和一氏に話を聞いた。
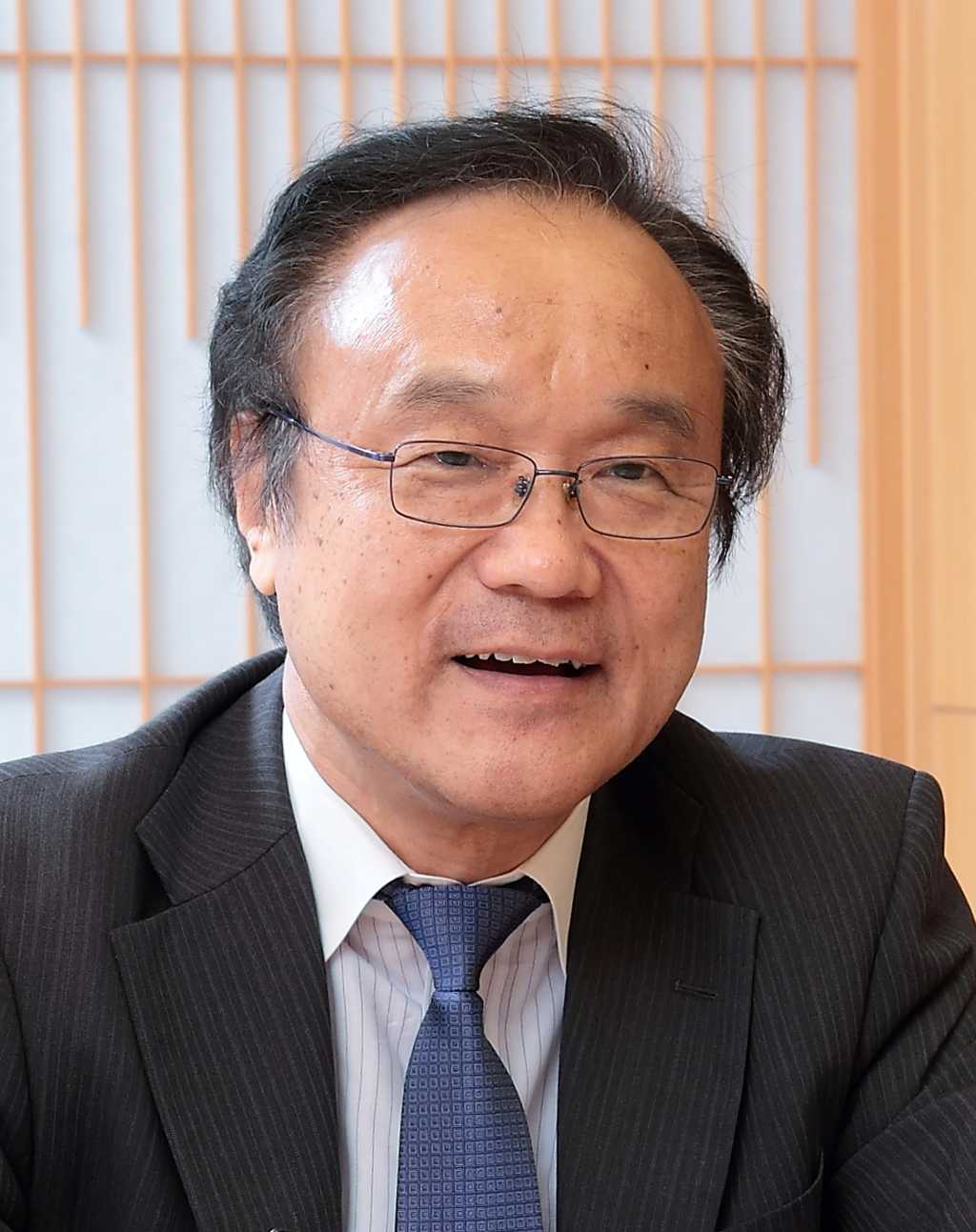
プロフィール:関口 和一 (せきぐち・わいち)
株式会社MM総研 代表取締役所長
1982年一橋大学法学部卒、日本経済新聞社入社。88年フルブライト研究員としてハーバード大学留学。89年英文日経キャップ。90〜94年ワシントン支局特派員。産業部電機担当キャップを経て、96年より2019年まで編集委員。2000年から15年間、論説委員として情報通信分野の社説を執筆。19年IT分野の調査コンサルティング会社、MM総研の代表取締役所長に就任。08年より国際大学グローコム客員教授を兼務。日本パブリックリレーションズ学会の特別研究会「失われた30年検証研究会」チーフリサーチャー。NHK国際放送コメンテーター、東京大学大学院客員教授、法政大学ビジネススクール客員教授なども務めた。著書に『NTT 2030年世界戦略』『パソコン革命の旗手たち』『情報探索術』(以上日本経済新聞社)、共著に『未来を創る情報通信政策』(NTT出版)、『新 入門・日本経済』(有斐閣)など。
垂直統合モデルの限界とグローバル競争の波
世界の産業競争は、「半導体を制する者が未来を制する」時代に突入した。米IT調査会社のガートナーグループの調査によると、2024年の世界の半導体市場は過去最高の6260億ドル(約100兆円)規模に達し、AI、EV、宇宙開発、量子コンピューティングなど、あらゆる先端技術の中核を担っている。半導体は単なる部品ではなく、国家の安全保障、産業基盤、そして技術覇権の根幹を成す「戦略物資」になったといえる。
日本はかつてこのグローバル競争の最前線に立っていた。1980年代後半から90年代初めにかけて、日本の半導体産業は世界市場の過半を占め、「日の丸半導体」と呼ばれる黄金期を築いた。1986年にはガートナーグループの半導体ランキングで1位NEC、2位日立製作所、3位東芝と1位から3位までを日本企業が独占、トップテンには6社がランキングされていた。
だがその栄光は、制度設計の歪みと構造的硬直によって、急速に失われていく。2024年の同社の調査ではトップテンに1社もランキングされていない。
日本の半導体産業の起点は、1953年に東京通信工業(現ソニーグループ)が米ウェスタン・エレクトリック社から製造特許を取得し、ゲルマニウムトランジスタの生産を開始したことにある。1955年には日本初のトランジスタラジオ「TR-55」が発売され、世界市場で大ヒット。この成功が、日立、NEC、東芝などの総合電機メーカーによる半導体産業への本格参入を促した。
1960年代には、日本が世界最大のトランジスタ生産国となり、半導体は国家の基幹産業へと成長。1970年代にはLSI(大規模集積回路)や半導体メモリーのDRAMの開発が進み、1986年には前述のように売上高ランキングで日本企業がTOP3を独占するまでに至った。NEC、日立、東芝――日本の総合電機型経営は、設計から製造、販売までを垂直統合で担い、社内に明確な用途(家電・情報機器)を持つことで、需要予測と投資判断の精度を高めることができた。
だが、1986年の日米半導体協定が転機となる。米国は日本企業による半導体のダンピング販売などを受け、安全保障上の懸念から、日本製半導体の台頭に強い警戒感を示し、日本政府に対して外国製品の市場シェア拡大を要求。これにより、日本企業は事実上の市場介入を受け、競争力を削がれていく。
日本政府は2000年代に入り、NEC・日立・三菱電機のDRAM部門を統合したエルピーダメモリ、日立と三菱のシステムLSI部門を統合したルネサステクノロジーなど、国産半導体企業の再編を主導した。しかし、親会社の意向を忖度する構造は変わらず、意思決定の遅れと責任の不明確さが競争力を削ぎ、エルピーダは2012年に破綻。最後の砦だった東芝も、2017年に半導体部門を分社化し、キオクシアとして独立。かつての総合電機メーカーとしての姿は完全に過去のものとなった。なぜ日本は半導体大国から凋落したのか。
世界を席巻した日本の半導体―垂直統合の出口戦略の強み
―― 日本が1980年代から世界の半導体市場を席捲しました。その理由はなんだったのでしょうか。
関口 日本の半導体産業がかつて世界をリードできた背景には、高度なものづくり技術と総合電機型の経営スタイルがありました。もともと半導体技術はアメリカで開発されたものですが、日本ではNECや東芝などの総合電機メーカーが本格的に参入しました。特に日本企業は、家電やパソコンといった明確な用途(出口)を持つ製品群を自社内に抱えていたことが大きな強みとなりました。この出口戦略の明確さにより、需要予測が容易で、設計から製造、販売までを垂直統合型の経営体制で効率的に運用することが可能でした。
さらに当時の日本では、半導体投資の規模がまだ小さく、事業部門の責任者レベルで柔軟かつ迅速な投資判断が可能だったことも成功要因の一つです。加えて、競争力の高い半導体製造装置メーカーや素材メーカーが国内に登場したことで、設計から製造、販売までを一貫して担える体制が整い、国際的な優位性を築くことができました。当時の日本は総合電機メーカーが半導体を製造していて、家電製品やパソコンなど半導体の供給先を社内に持っていたことが幸いしました。
―― 1990年代初めまで世界を席巻していた日本の半導体産業がなぜ、凋落したのでしょうか。その根本原因は技術、政策、企業文化のどこにあるのでしょうか。
関口 日本の半導体産業が競争力を失った背景には、単一の原因ではなく、複数の要因が複雑に絡み合っています。中でも最大の転機となったのが、「日米半導体協定」に象徴される政策的な失敗です。半導体市場は当初、アメリカが圧倒的なシェアを握っていましたが、日本企業が急速に技術力と生産能力を高め、世界市場で存在感を強めていきました。しかしアメリカにとって半導体は国防産業の中核でもあり、安全保障の観点から日本に主導権を握られることへの警戒感が高まりました。こうした世論の高まりを受けて、米政府は日本に対して市場開放を強く求めるようになります。
一方、日本側は総合電機型の経営スタイルにより、社内需要を背景に大量生産を進めていました。これによりシェアは拡大しましたが、価格競争の激化によってダンピングと見なされる事態を招きました。加えて、日本企業には「自前主義」が根強く、自社の製品にアメリカ製半導体を積極的に採用しない傾向がありました。
こうした状況の中で、1986年に締結された日米半導体協定の第一期では、日本政府が外国製半導体の市場シェアを協定には明記されていない「サイドレター」(秘密文書)によって20%に引き上げることを約束します。これは事実上の市場介入であり、国内産業構造に大きな影響を与えるものでした。さらに第二期協定では、この市場開放のシェア目標が明文化され、日本の半導体産業に対する構造的な転換圧力が本格化します。これにより、日本企業の競争力は徐々に低下し、グローバル市場での地位も後退していくことになります。
シリコンサイクルと総合電機モデルの脆弱性
―― 技術的な偏りや企業文化の問題もあったのでしょうか。
関口 日本は1980年代後半、世界の半導体市場の5割以上を占めていましたが、その多くがDRAMであり、垂直統合型モデルだったことから、論理演算に利用するロジックやASIC(特定用途向け集積回路)などへの転換が遅れてしまいました。その結果、利幅が取れなくなり、商売としての魅力が薄れていきました。さらに、DRAMの容量が増えるにつれて、設備投資の規模も膨らみました。最初は事業部長レベルで投資判断ができたものが、規模が大きくなると会社全体の意思決定が必要になり、トップが専門外だと判断が遅れてしまう。総合電機の強みが、逆に足かせになってしまったのです。一方で、海外では設計と製造を分けた水平分業型への移行が進み、巨大なファウンドリー(受託製造会社)が登場しました。日本は垂直統合に固執した結果、投資額の拡大とともにタイムリーな投資ができなくなり、競争力を大きく損なうことになりました。
―― 日本企業はシリコンサイクルへの対応が難しかったという指摘もありますが、どうでしょうか。
関口 シリコンサイクルはボラティリティ(変動要素)が高く、総合電機メーカーにとっては業績への影響が大きすぎる。だから半導体事業を切り離そうとしたわけです。三菱電機の当時社長だった北岡隆さんが早い段階でそれを決断しましたが、当時は批判も多かった。ただ、結果的には正しい判断だったと思います。
―― サムスン電子をはじめ、海外の半導体メーカーの台頭も日本の半導体産業の凋落に拍車をかけたのではないですか。
関口 韓国のサムスン電子に象徴される新しいプレーヤーの登場は大きな要因だったと思います。サムスンはオーナー経営なので、意思決定が速い。大規模投資もスピーディに進められる。日本は縦割りで横並びの文化が強く、水平分離型へのモデル転換ができなかった。垂直統合型は半導体の最初のフェーズでは有効でしたが、規模が拡大すると柔軟性が失われ、機敏に対応できなかったのが問題だったと思います。
―― サムスンはなぜ急激に力を付けたのでしょうか。
関口 1990年代以降、日本のバブル経済が崩壊したことで、日本メーカーが投資を控えるようになったことが大きいと思います。また日本企業のリストラや定年制度により大量の技術者を退職させたことから、韓国企業が高額で彼らを採用しました。結果として、日本の技術のブレーン流出が起きてしまった。これが日本メーカーの競争力低下と韓国の競争力強化につながった面があります。
―― 海外企業の台頭は、当時は円高の影響も大きかったのではないでしょうか。
関口 1985年のプラザ合意以降、急激に円高が進みました。ちょうど1986年に日米半導体協定が結ばれたタイミングでもあり、日本は円高不況に突入して、海外で物が売りにくくなった。さらに1990年には総量規制によって不動産バブルが崩壊し、企業の投資意欲も一気に冷え込んだ。これが半導体産業にも大きな影響を与えました。それまでのような「イケイケドンドン」の投資ができなくなってしまったのです。
政府主導の再編と「日の丸連合」の限界
―― 通商産業省(現経済産業省)は半導体産業を立て直すために、業界再編を進めようとしたわけですが、うまくいかなかったようですね。
関口 通産省はメインフレーム時代の3大コンピューターグループ(富士通+日立、NEC+東芝、三菱電機+沖電気)への再編をモデルにして、半導体事業のグルーピングを進めました。 その後、政府主導で「日の丸連合」を形成することになり、NEC、日立、三菱のDRAM事業を統合したエルピーダメモリ、日立と三菱のシステムLSI事業を統合したルネサステクノロジーなどが誕生しましたが、元の企業から分社化して作った連合体だったため、意思決定が遅く、責任も不明確で、結局、エルピーダは米マイクロンテクノロジーに買収され、日本の半導体産業はグローバルな競争に飲み込まれてしまいました。液晶分野でも同じような失敗がありました。親会社のメンツを立てすぎると、柔軟な再編ができないわけです。
―― 垂直統合型の日本の大手半導体メーカーはほとんど姿を消しましたが、素材メーカーや装置産業がまだ健在です。これは日本の半導体産業の復興につながるのではないですか。
関口 半導体メーカーは国内の製造工程に莫大な投資が必要ですが、装置や素材メーカーは海外市場にも展開できるため、国内市況が悪化していても需要さえあればビジネスが成立します。ただし、これらの装置や素材を長年にわたり海外に供給してきた結果、韓国などのメーカーが力をつけたという側面もあります。韓国は半導体の完成品では強みを持っていますが、部品や素材の多くは今なお日本に依存しているのが現状です。しかしその一方で、国内に優れた装置メーカーや素材メーカーが残っていたからこそ、今後の日本の半導体産業の盛衰のカギを握るラピダスの誕生やTSMCの日本進出が可能になったといえるのではないでしょうか。
―― 日本が今後、半導体産業を再興するには、何が必要でしょうか?
関口 新型コロナウイルスの影響で、世界的に半導体が不足し、サプライチェーンが寸断されました。その結果、自動車のような産業機械向けの半導体ですら、安定して供給できない状況が生まれました。これまでの日本は、「部品は安いところから買えばいい」という調達方針で、海外依存を前提にしてきました。こうしたグローバル調達志向は世界経済がうまく機能している時は正しい判断だと思いますが、危機の時には通用しません。やはり、一定の製造能力を国内に持っておくことが不可欠です。半導体は、単なる部品ではなく、産業全体の神経系とも言える存在です。日本の産業競争力を守るためには、半導体の製造・供給体制を自国で再構築することが、極めて重要な課題だと考えています。








