日本の半導体産業が再び世界の檜舞台に立てるのか――。ラピダスが2ナノ世代のGAAトランジスタ試作に成功し、国策企業としての第一歩を踏み出した。だが、量産化には5兆円規模の資金と高度な人材確保が不可欠であり、復権の道は険しい。日本はかつて世界の半導体市場を席巻する黄金期を築いたが、1990年以降急速にその力を失った。果たしてラピダスの誕生によって、日本の半導体産業は再び復権することができるのか、世界の情報通信分野の最新トレンドを長年取材してきた日本屈指のITジャーナリストであり、日本パブリックリレーションズ学会の特別研究会「失われた30年検証研究会」チーフリサーチャー、IT調査コンサルティング会社、MM総研の代表取締役所長である関口和一氏に話を聞いた。
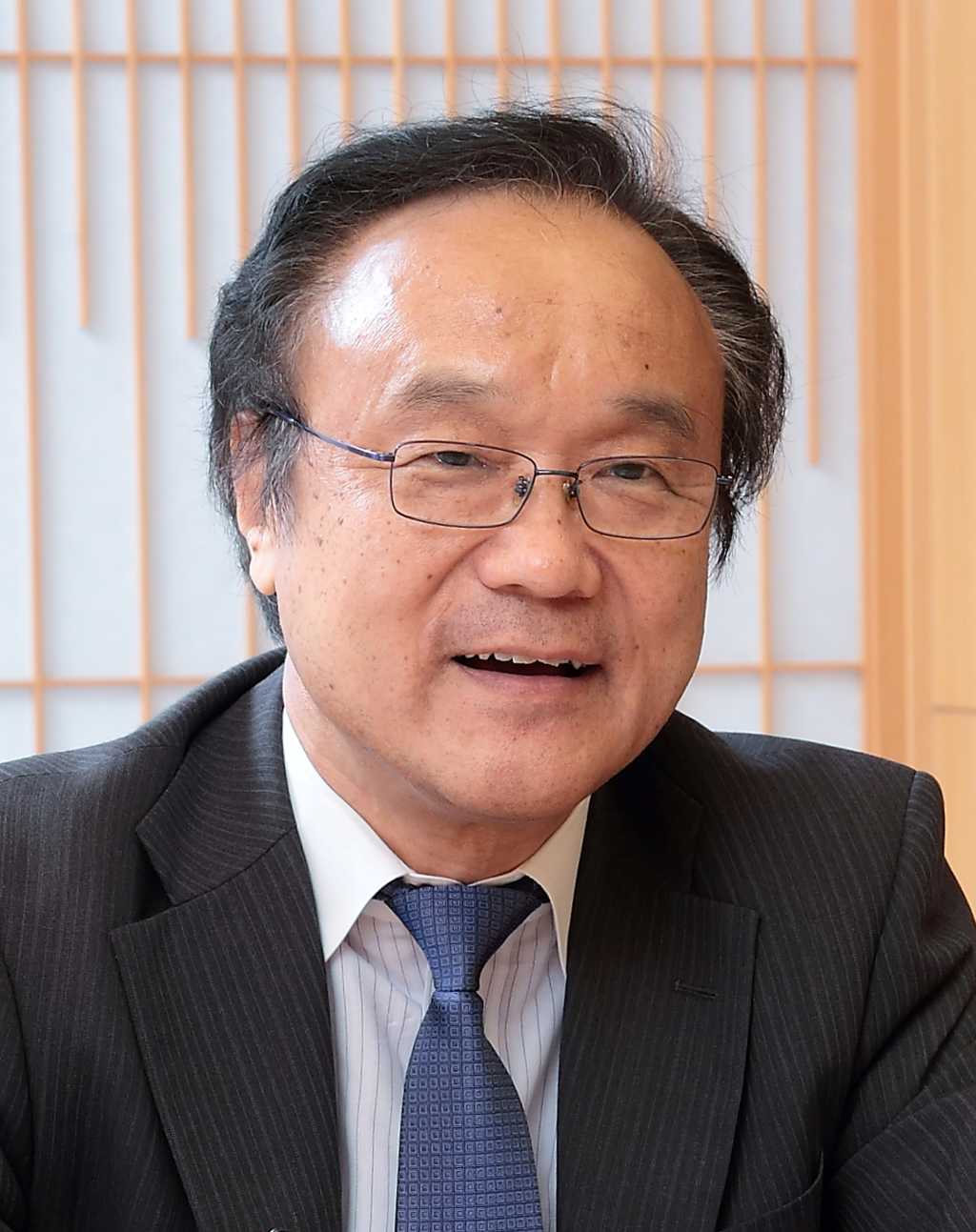
プロフィール:関口 和一 (せきぐち・わいち)
株式会社MM総研 代表取締役所長
1982年一橋大学法学部卒、日本経済新聞社入社。88年フルブライト研究員としてハーバード大学留学。89年英文日経キャップ。90〜94年ワシントン支局特派員。産業部電機担当キャップを経て、96年より2019年まで編集委員。2000年から15年間、論説委員として情報通信分野の社説を執筆。19年IT分野の調査コンサルティング会社、MM総研の代表取締役所長に就任。08年より国際大学グローコム客員教授を兼務。日本パブリックリレーションズ学会の特別研究会「失われた30年検証研究会」チーフリサーチャー。NHK国際放送コメンテーター、東京大学大学院客員教授、法政大学ビジネススクール客員教授なども務めた。著書に『NTT 2030年世界戦略』『パソコン革命の旗手たち』『情報探索術』(以上日本経済新聞社)、共著に『未来を創る情報通信政策』(NTT出版)、『新 入門・日本経済』(有斐閣)など。
ラピダス、2ナノ試作開始──国産半導体復権への軌跡
2025年7月18日、日本の半導体産業にとって歴史的な一歩が刻まれた。最先端半導体の量産を目指すラピダスが北海道千歳市の製造拠点「IIM-1」にて、2ナノメートル(nm)世代のGAA(Gate-All-Around)トランジスタの試作に成功したと発表した。この成果は、単なる技術的進展ではなく、日本の経済安全保障と産業競争力を左右する国家戦略の象徴でもある。
ラピダスは2022年、トヨタ自動車、ソニーグループ、NTTなど国内主要企業の出資により設立された。背景には、かつて世界を席巻した日本の半導体産業が、1990年代以降、台湾の受託製造会社、TSMCや韓国のサムスン電子などに後れを取ったという危機感がある。政府はこの流れを断ち切るべく、ラピダスを「国策半導体企業」と位置づけ、2025年度までに累計1兆7,225億円の支援を決定している。
ラピダスの技術的中核は、米IBMとの協業による次世代半導体の加工技術であるGAA構造の採用と、極紫外線(EUV)リソグラフィ装置の導入にある。従来のFinFET(フィン型電界効果トランジスタ)構造に比べ、GAAは消費電力を約40%削減しつつ、性能を10%向上させるといわれる。2024年末にはクリーンルームが完成し、2025年4月には露光・現像工程に成功し、7月には初の試作品が製造され、2026年3月までに顧客向けサンプルの提供を目指している。そして2027年の量産開始を目標に、工程管理の厳密化と顧客開拓を進めている。
とはいえ、試作成功はあくまで通過点であり、量産化にはさらなる資金調達が不可欠だ。現在、トヨタやソニーなど8社からの出資額は約73億円、政府からは累計約9200億円が投じられているが、2ナノ相当の先端半導体を量産するには総額5兆円が必要とされる。政府・民間双方からの追加出資が求められる一方で、事業の採算性や国際競争力に対する懐疑論も根強い。TSMCですら3ナノまでしか量産していない現状を踏まえると、歩留まり率の向上や製造体制の確立には高度な技術力と時間が不可欠である。 AI(人工知能)、自動運転、創薬など、次世代産業に不可欠な最先端半導体の国産化は、日本の未来を左右する挑戦だ。今回の試作成功は、その挑戦が単なる夢物語ではなく、現実の技術的基盤に根ざしたものであることを示している。では、こうした取り組みを日本の半導体産業復興に結び付けるには、どのようにしていけばいいのか関口氏に尋ねた。
ラピダス試作成功は「復権」か?──象徴性と現実のギャップ
―― ラピダスが2ナノの半導体試作に成功しました。これは日本の半導体産業の復権につながるのでしょうか。
関口 ラピダスの試作成功は象徴的な成果ですが、それだけで「復権」と言えるかは慎重に考えるべきです。復権の定義にもよりますが、かつてのように日本の半導体メーカーが世界市場を席巻するような状況に戻るのは、現実的には非常に難しいといえます。日本にはグローバル競争力を持つ半導体メーカーがほとんど残っていないといえるからです。
ただし、国内の需要にある程度応えられる体制を再構築することは可能です。ラピダスはそのきっかけのひとつです。コロナ禍で半導体のサプライチェーンの脆弱性が露呈したことで、国内に半導体製造技術を持つことの重要性が再認識されました。日本が再び重要な役割を果たすための土台づくりとして、ラピダスには大きな期待が寄せられています。
―― ラピダスの取り組みを今後も続けていくためには何が必要でしょうか。
関口 最大の鍵は、政府と産業界がどれだけ継続的に支援できるかです。ラピダス設立の背景には、半導体不足によるサプライチェーンの混乱があります。半導体がなくて自動車が製造できないといった事態が起きたことで、「部品は安いところから買えばいい」という従来の調達方針が限界を迎えました。
これを機に、日本国内でも「ある程度は自分たちで半導体の製造能力を持つべきだ」という認識が広まりました。今後、ラピダスが本格的に量産体制に入ったとき、それが持続可能かどうかを見極めたうえで、政府や企業がどれだけ資金を投入できるかが成否を分けるカギだと思います。
―― 資金も重要ですが、人材不足も深刻ではないでしょうか?
関口 人材の枯渇は資金以上に深刻な課題です。一度産業が止まると、特に理系人材は職がなければその分野に戻ってきません。ラピダスには社長の小池淳義氏や会長の東哲郎氏のような立派な経営者がいますが、事業を立ち上げるには現場で指揮をとれるエンジニアが必要です。そうした人材が日本は不足しており、事業の立ち上げには相当な困難が伴います。人材確保は資金調達と並ぶ最大のポイントです。
―― 海外から人材を調達することはできないのでしょうか?
関口 理論的には可能ですが、現実的には難しいと思います。日本には年功序列型の文化があり、職種ごとの給与レンジが固定されています。優秀なエンジニアに対して社内規定以上の報酬を支払うという発想がなく、海外の人材を引きつけるには制度面での改革が必要です。AI分野でも同様の課題がありますが、グローバルな人材獲得競争に勝つためには、報酬体系や職場文化の柔軟化が不可欠です。
国際協業の時代へ──台湾・韓国・米国との連携戦略
―― 米中対立や経済安全保障の文脈で、日本の半導体産業はどのような役割を果たすべきだとお考えですか。
関口 日本は今後、半導体を国家の安全保障と技術主権を左右する「戦略物資」として位置づけ、国内供給体制を強化すべきです。現在、世界の半導体製造は台湾のファウンドリーに大きく依存しており、仮に台湾有事などで製造が停止すれば、グローバルなサプライチェーンは深刻な影響を受けます。
こうした地政学的リスクを踏まえ、TSMCが熊本県に工場を設立したことは、供給安定化を目的とした重要な布石です。半導体は小さいので一カ所で集中して製造し、空輸するのが効率的で、自動車のように分散生産に合わないという特性があります。しかし様々な要因によりそうした形で海外から調達できなくなる可能性があるなら、日本国内に安定した製造拠点を持つことが不可欠となります。ラピダスのような国策企業は、経済安全保障の観点からも極めて重要な存在です。
IBMがラピダスの技術パートナーとして関与しているのも、自社に製造能力を持たないIBMが、日本を技術実装の受け皿として選んだ戦略的判断です。米マイクロンテクノロジーによるエルピーダメモリの買収も、同様の文脈で理解できます。また、半導体不足によって日本の自動車メーカーが生産停止に追い込まれた事例は、製造業全体の安定操業にとって半導体供給がいかに重要かを示しています。
―― 今後は日本単独ではなく、国際協業が鍵になりそうですね。
関口 その通りです。日本は台湾、韓国、米国といった主要国と、戦略的かつ柔軟な協力関係を築く必要があります。台湾とは、対中国という地政学的な文脈も含めて、より深い協力関係を築くべきです。たとえば、2024年8月に台湾の国営通信会社だった中華電信とNTTが次世代光通信基盤「IOWN」の高速ネットワーク技術「APN」による接続実験に成功しました。これは3000㎞離れる台北と東京を遅延なく結び、今後の産業協力を加速させる重要な布石となりました。
韓国は家電や半導体分野で日本を凌駕する競争力を持つ一方で、部品や製造装置の調達では依然として日本に依存しています。敵対関係ではなく、技術力を高め合うライバルとしての健全な協力関係を築くことが望まれます。ただし、韓国側には「自分たちが一番になりたい」という強い意識があるため、協力関係の構築には工夫が必要です。
米国とは経済面でも安全保障面でも密接不可分な関係にあります。ラピダスの設立に際しては、IBMの技術支援が大きな後押しとなりました。米中関係と比較すれば、日米関係は極めて友好的であり、今後はウィン・ウィンの関係を維持・強化していくことが求められます。すでにTSMCとソニーの協業、ラピダスとIBMの連携など、日米連携の動きは始まっています。日本単独での産業再興は現実的ではなく、海外の技術・資本・人材を活用しながら、守るべき領域は戦略的に守るというバランス感覚が不可欠です。








