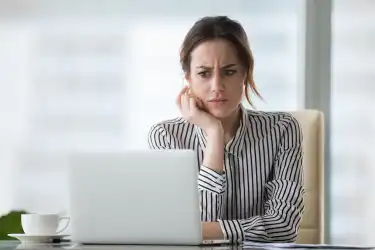ウェブサイト改ざんは、見た目を変えずに訪問者を危険なサイトへ誘導する「静かな脅威」へと変化しています。本記事では国内の最新事例などを基に、巧妙化する手口の実態と、すべてのサイト運営者に求められる現実的な防御策を解説します。

巧妙化し、日常に潜むウェブサイト改ざんの脅威
現代におけるウェブサイト改ざんの最も恐ろしい特徴は、その「不可視性」にあります。攻撃者はサイトの外観を一切変えることなく、水面下で不正なコードを仕込みます。その目的は、単なる愉快犯的な自己顕示欲の満足ではなく、明確に金銭的な利益を狙ったものです。代表的な手口として挙げられるのが、訪問者をオンラインカジノや偽の通販サイト、フィッシングサイトへと自動的に転送する「リダイレクト型」の改ざんです。サイトの設定ファイルである「.htaccess」や、ウェブページを動的に生成するプログラム言語「PHP」のソースコードに数行の不正な記述を挿入するだけで、訪問者は意図せずして危険な領域へと足を踏み入れてしまいます。
さらに巧妙な手口として、検索エンジンを経由してアクセスしてきたユーザーだけを標的にする「ステルス型」あるいは「検索汚染型」と呼ばれる攻撃も横行しています。サイト運営者が直接URLを入力して表示を確認しても異常は見られず、一般のユーザーが検索結果から訪れた場合にのみ不正なページが表示されるため、発覚が大幅に遅れるケースが後を絶ちません。この手口は、検索結果そのものに偽の情報を紛れ込ませることで、組織のブランドイメージを長期にわたって毀損する深刻な二次被害をもたらします。
また、サイトに埋め込まれた不正なJavaScriptコードによって、訪問者のブラウザ上で仮想通貨を採掘させる「クリプトジャッキング」や、不審な広告を大量に表示させる「アドウェア」の混入も、攻撃者にとって効率的な収益化手段として定着しています。これらの攻撃は、サイトの表示速度を低下させる程度の軽微な影響しか及ぼさないことも多く、多くのユーザーは自身のコンピュータが悪用されていることに気づかないまま、知らず知らずのうちに攻撃者の懐を潤す手助けをしてしまうのです。
このような静かなる攻撃の温床となっているのが、WordPressに代表されるCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)の普及です。手軽に高機能なサイトを構築できる反面、その本体や無数のプラグイン、テーマに存在する脆弱性が、攻撃者にとって格好の侵入口となります。パスワードを片端から試す「ブルートフォース攻撃」や、他のサービスから流出したパスワードリストを用いた不正ログインも依然として有効な手段であり、一度管理者権限を乗っ取られてしまえば、攻撃者は意のままにサイトの内部構造を改変することが可能になります。もはやウェブサイト改ざんは、一部の組織を狙った特殊なサイバー攻撃ではなく、日々の運用管理の隙を突かれる「生活習慣病」のような、あらゆるサイト運営者にとって身近なリスクとなっているのです。
官民学に広がる被害の実態——誰が、どのように狙われているのか
ウェブサイト改ざんの被害は、特定の業界や組織規模に限定されるものではありません。むしろ、社会的な信頼性が高く、多くの人々がアクセスするサイトほど、攻撃の踏み台としての価値が高まり、標的になりやすいという現実があります。その実態は、近年公表された被害事例からも明らかです。
2025年10月、国土交通省が運営するウェブマガジンにおいて、閲覧時に偽サイトへ誘導される事象が確認され、サイトが一時閉鎖される事態に至りました。政府系サイトという高い公共性と信頼性を逆手に取ったこの事例は、国の中枢機関ですら改ざん攻撃と無縁ではないという事実を社会に突きつけました。同様に、教育機関も主要なターゲットの一つです。2025年9月には、国立大学法人である東京外国語大学の公式サイトが改ざんされ、オンラインカジノサイトへ誘導される被害が発生しました。大学のサイトは、在学生や教職員、受験生といった幅広い層が頻繁に利用し、検索エンジンからの流入も非常に多いという特徴があります。攻撃者はこうした特性を熟知しており、検索結果経由のアクセスのみを狙い撃ちすることで、被害の潜在化と長期化を図ります。教育という公的な使命を担う機関の信頼が、サイバー攻撃によって静かに蝕まれていくのです。
民間企業においても被害は深刻です。大手上場企業であるアイ・エス・ビーは2025年5月、自社のホームページが改ざんされ、閲覧者が不正サイトに誘導される可能性があると公表しました。幸い、情報流出の可能性は低いとの調査結果が示されましたが、たとえ直接的な情報漏洩に至らなくとも、企業の公式サイトが攻撃者の支配下に置かれたという事実は、株主や顧客の信頼を大きく損なうものです。また、あるコンサルティング会社の人材紹介サイトでは、訪問者を外部サイトへ転送するだけでなく、検索エンジンに不正な情報を登録させる「検索汚染」まで行われていたことが報告されています。この種の攻撃は、サイトを復旧させた後も、検索結果に不審な文字列が残り続けるため、企業の評判に対するダメージが尾を引くという厄介な側面を持っています。
さらに、私たちの生活に身近な地方自治体やその関連団体も例外ではありません。滋賀県草津市のコミュニティ事業団のサイトでは閲覧者がフィッシングサイトへ誘導され、横浜市の学習支援サイトでは無関係な通販サイトが表示される被害が確認されました。2025年10月には、岡山県が運営する複数のPRサイトで不正アクセスと改ざんの痕跡が見つかり、一部が公開停止に追い込まれています。地域の文化や教育、観光といった、地域社会の活力を支える情報発信の拠点までもが、容赦なく攻撃の対象とされているのです。
これらの事例を俯瞰して見えてくるのは、攻撃者が組織の種類を選ばないという冷徹な事実です。彼らにとって重要なのは、サイトの脆弱性という「侵入のしやすさ」と、アクセス数の多さという「収益化の効率」に他なりません。ウェブサイトの運用管理における少しの油断、例えばソフトウェアの更新漏れや安易なパスワードの設定といった、ごくありふれた不備が、深刻なセキュリティインシデントへと直結してしまう。それが、日本のウェブ空間が直面している偽らざる現実なのです。
侵入を前提とした、現実的な防御戦略とは
巧妙化・常態化するウェブサイト改ざんの脅威に対し、「絶対に侵入させない」という完全防御を目指すことは、もはや現実的ではありません。これからのウェブサイトセキュリティは、侵入される可能性を常に念頭に置く「侵入前提」の考え方に立ち、被害の発生をいかに迅速に検知し、影響を最小限に食い止め、そして適切に復旧・報告するか、というインシデントレスポンスのサイクルを確立することが極めて重要になります。
万が一、改ざんの疑いが生じた場合にまず実行すべきは、被害の拡大防止と証拠保全です。具体的には、直ちに該当サイトをネットワークから隔離し、公開を停止します。これにより、新たな訪問者が被害に遭うことを防ぐと同時に、攻撃者によるさらなる内部侵入や証拠隠滅の試みを遮断します。次に、サーバーやCMSの管理画面、データベース、そして攻撃の痕跡が記録されているアクセスログなど、調査に必要となるあらゆるデジタルデータを保全します。この初期対応の的確さが、その後の原因究明と、顧客や社会に対する説明責任を果たせるか否かを大きく左右します。パスワードの即時変更や、関連するシステムの脆弱性診断も、二次被害を防ぐために並行して進めるべき必須の作業です。
こうした事後対応に追われる状況を避けるためには、日々の運用における地道な恒久対策が不可欠です。技術的な側面では、まず攻撃の起点となりやすいCMS本体、テーマ、プラグインを常に最新の状態に保ち、不要なコンポーネントは徹底的に削除して、攻撃者が利用可能な侵入経路(アタックサーフェス)を極力減らすことが基本となります。管理者アカウントには、パスワードに加えてスマートフォンアプリなどを用いた多要素認証を必須とし、特定のIPアドレスからしかアクセスできないように制限をかけることで、不正ログインのリスクを大幅に低減できます。さらに、ファイルの改ざん検知システムを導入して、ウェブサイトを構成する重要なファイル群の変更を常時監視し、異常があれば即座に管理者に通知する仕組みを整えることも有効な対策です。
しかし、技術的な対策だけでは万全とは言えません。それを補完するのが、運用面での取り組みです。Google Search Consoleのようなツールを用いて、自社サイトが検索エンジンにどのようにインデックスされているかを定期的に監視し、不審なページが登録されていないかを確認する作業は、「検索汚染」の早期発見に繋がります。また、インシデントが発生した際の報告・連絡・相談の体制を明確に定め、対応計画書として文書化し、定期的に訓練を行うことで、有事の際にも組織として冷静かつ迅速に行動できるようになります。
最終的に、ウェブサイトの信頼を守るための鍵は、「完全防御の幻想」を捨てることにあります。攻撃者は常に私たちの防御網の脆弱な一点を探し出し、そこを突破しようと試みてきます。その攻撃をいち早く検知し、速やかにサイトを正常な状態に復旧させ、何が起きたのかを真摯に説明する。この「早期検知・即応復旧・説明責任」という不断のサイクルを回し続けることこそが、現代のウェブサイト運営者に求められる、最も現実的で誠実なセキュリティへの向き合い方なのです。官民学の別なく、すべての組織がこの現実を直視し、技術と運用の両輪で、自らの情報発信の砦を着実に守り固めていくことが、今まさに問われています。